
自社ワイナリー建設の経緯
どうやったら、もっとオーガニックを身近にできるのか?
もっとバイオダイナミック農法を身近に感じてもらえるのか?
そのような問いが私たちのワイン事業の出発点です。
当時ヨーロッパだけでなくチリなど世界中でナチュールワインのシェアが拡大してきており、バイオダイナミック農法で育てられた「ビオディナミワイン」の認知度は年々広がっていました。
今後もビオディナミが認知、浸透していくのは「ぶどう」ではないか?オーガニックワイン=ぶどうを栽培を通し、ビオディナミのワインを作っていくことで、今までよりももっと広がりを期待できるのではないか?
そのような思いから、私たちの活動はスタートしました。
北海道がワイン用ぶどうに適した気候になってきたことや、山幸という品種が開発されたことも私たちの背中を押してくれました。

ぶどう苗を植えるトカプチメンバー
2013年、私たちの本拠地は十勝ですが、そこから車で2時間半ほどかかるけれど気候的に栽培に適した上富良野に土地を購入。翌年、初めてワイン用ぶどうの苗を定植。でもすぐにぶどうが採れるわけではありません。最初の4年は何もできないような状態から始まって、5年目からやっと収穫ができるようになりました。
醸造はまず岩見沢の10Rワイナリーブルースさんに委託しました。ぶどうと一緒に社員も行ってナチュラルワインの醸造をイチから学び、自分たちの思い描くワインが作れるようになるために修行しました。
そして2023年、10年越しにようやく畑のすぐそばに自社ワイナリーが建ち、自分たちのぶどうを自分たちのワイナリーでワインにできる、テロワールを最大限に表現できる環境が整いました。

一年で一番忙しい収穫期
ワイナリー建設は、新月の日に更別のトカプチ農場の森のカラマツの木を伐採して、自分たちで製材し、地元のログハウスビルダーの方と一緒に行いました。
上から見ると八角形が2つくっついているような形、1つが醸造所、1つが醸造庫になっています。(実際は醸造庫は土に埋まって見えません)
レムニスカート、無限の形、八の字、生命の流れ、水や風の流れ、無限の可能性、循環、円環、場が良くなるといったイメージを具現化してこのような形になりました。

バイオダイナミック農法で育てる理由
葡萄畑はバイオダイナミック農法で宇宙のエネルギーをいかに土壌に引き込むか、そして元気なブドウを作れるかということを意識しています。
バイオダイナミック農法は自然由来の「調剤」というものを使います。自分たちで作った調剤を自分の手でまくということがバイオダイナミックを作り上げるには重要なのではないかと考えています。

500番 牛糞牛角調合剤
バイオダイナミック農法を通して実現したいのは、調剤を使うことによって場を整え、場を整えることでエネルギーをぶどうに込める、そしてエネルギーのあるブドウを収穫することで、エネルギーのあるワインを作る、ということです。
ワインの美味しさ以上に、私たちのワインを飲んで、
「なんかこれすごい!?」「なんかこれ違うよね」
と思っていただけるようなワイン作りを目指しています。
エネルギー、と言われても、ピンと来ないと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、そもそも、醸造だったり、発酵だったり、私たちはそういうこと自体がエネルギーを引き込む作業だと思っています。
塩につけることや砂糖につけることによって食べ物を長持ちさせることにつながります。
腐敗ではなく発酵に導いていくこと、酸化してしまうのではなく不酸化へ持っていくこと、これをエネルギーを高めるという作業だというふうに思っています。
なので私たちはチーズ、パンなど、発酵に関わるモノづくりが多いです。
テロワールを表すワイン作りを
私たちは、その土地や、自然環境、そこで育ったからこそ、そこで熟成されたからこそ生まれる味があると考えています。つまり、テロワールをとても大事にしています。
だからこそ、ぶどうを育てるヴィンヤードに人の手を加えるのは最小限に。
畑の周りにくるみや白樺、イタヤカエデなどの樹々を植えて排水性や風の通りをデザイン。花の咲く植物を畑の周りに植えることで、さまざまな虫や動物が集います。豊富な生態系によりぶどうの害虫のみが発生することを防いでいます。また、ぶどうの畝間にはライ麦をまき、根を伸ばすことで硬盤層を破壊し、ぶどうの根が地中深くまで入りやすいように設計。地中深く伸びた根は畑の微量要素も吸い上げ、果実の味に影響を与えてくれます。このように、自然と調和する畑作りを大切にしています。

シャイな羊たちが逃げていく
醸造の方法は全てナチュールワインやビオディナミワインと言われる作り方です。その中でも徹底してその製法にこだわっています。酵母は自然酵母のみですし、ノンフィルター、濁りを除去する濾過もしない…など、できるだけ自然の状態で絞っています。
醸造も木樽やステンレスタンクも併用しつつ、基本的にはテラコッタと言う土から作った壺で醸造するやり方を採用しています。テラコッタは、日本からイタリアにパイカエースという特別な水を送り、それを使って土をこねてもらい、焼き上げたものです。
ジョージアなどでこの醸造方法が古くから行われていて、通常は土に埋めて熟成させますが、日本では地震があり壺にヒビが入ってしまうことを懸念し、地上に出す形での熟成になりました。

なんだか可愛いテラコッタたち
可能性を秘めた山幸
フランスのピノノワールなど素晴らしい品種があることも知った上で、日本には日本の風土にあった品種を育てることが大事だと考え「山幸」という品種でワイン作りをしています。
山幸は十勝池田町で開発されたセイベルをクローン選抜した清美と、山葡萄の後輩品種で、灰色かび病などの病気に強くて耐寒性があり、冬でも苗を雪の下に覆う必要がありません。山幸は現在では、世界のワイン用ぶどうの一つとして正式に認定されています(OIV認定)

果実はとても甘くて酸っぱい
その特徴的な味わいは一口飲んでいただければ一目瞭然。フルーティな味わいであったかと思えば、スパイシーな風味も楽しめる、魅惑のぶどうです。他の北海道ワインと飲み比べていただくと、「暴れ者」という印象さえあるかもしれません。それほどに山葡萄本来の野生味を引き継いでいるのだと思います。
また、同じ山幸でワインを作っても、その土地や環境、そして醸造家の考え方でその味わいは全く変わっていきます。私たちは日本、上富良野、トカプチでしか作れないワインを作りたいと考えています。
そんなワインが作れれば、飲んでいただいた方々に自然豊かでさまざまな生物が行き交い、心地よい風が吹くこの上富良野の大地を思い起こしていただけるのではないかと思っています。

年々、ぶどうの収穫量も増え、その分収穫の協力者も増え、飲み手も増え、その輪の広がりを実感しています。ここが北海道のオーガニックビレッジの中心となり、豊かにテロワールを楽しむ時が刻まれていくことを切に願っています。
(2024日本のオーガニック最先端の旅にてアグリシステム及びトカプチメンバーがツアー参加者に向けてお話したことがベースになっています)
 北海道オーガニックヴィレッジ
北海道オーガニックヴィレッジ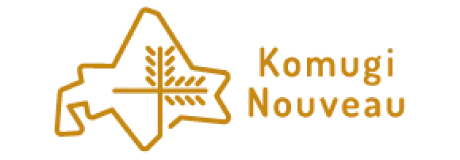 北海道小麦ヌーヴォー
北海道小麦ヌーヴォー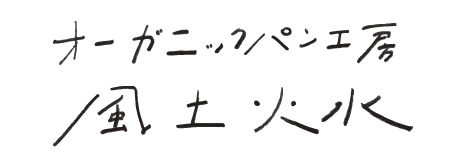 オーガニックパン工房「風土火水」
オーガニックパン工房「風土火水」 自然食品店「ナチュラル・ココ」
自然食品店「ナチュラル・ココ」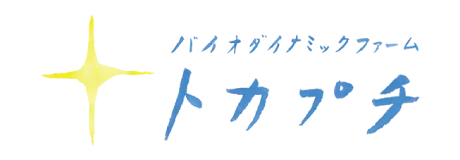 バイオダイナミックファーム トカプチ
バイオダイナミックファーム トカプチ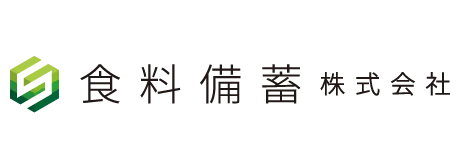 食料備蓄株式会社
食料備蓄株式会社 未来を変えるパン 検索マップ
未来を変えるパン 検索マップ